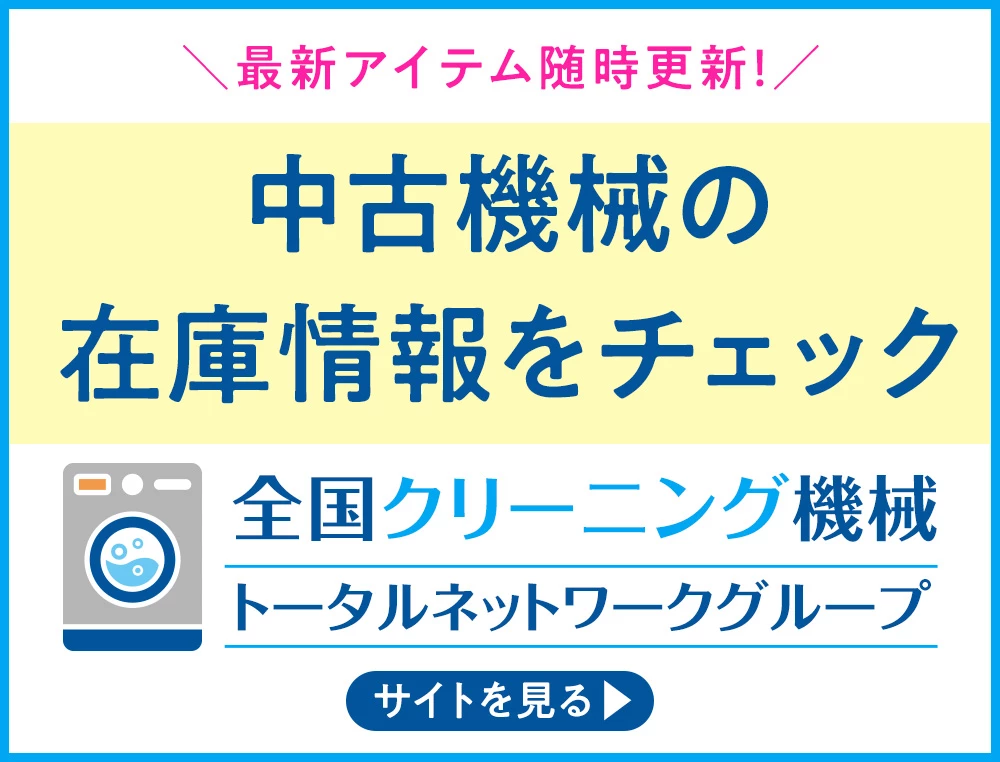【障がい者雇用】クリーニング業内製化における障がい者雇用の取り組み

「単純作業だから障害をお持ちの方に向いている」という固定観念に、あなたは疑問を感じたことはありませんか?実はクリーニング業界では、多様な特性を活かす働き方が40年前から進化し続けています。某クリーニング企業では全従業員47名中28名が障害者で、知的・身体・精神と幅広い特性を持つ方々が活躍中。この数字が示すのは、単なる雇用ではなく真の職場適応の可能性です。
1980年代、同社が知的障害者の受け入れを始めたきっかけは、ある知人の切実な要請でした。当時は「特別な配慮が必要」との声もありましたが、業務の内製化を通じて徐々に体制を整備。現在では23名の知的障害者に加え、身体障害者3名、精神障害者2名がそれぞれの強みを発揮しています。
クリーニング工程の分解と再構築が、なぜ多様な人材の活躍を生むのでしょう?実は衣類の検品から仕分け、機械操作まで、を分析し段階的な作業分解が特性に応じた役割分担を可能にしています。この取り組みが企業経営に与える好影響は、単なるCSRを超えた経営戦略の本質を問いかけます。
この記事のポイント
- クリーニング業界で60%近い障害者雇用率を実現した具体的事例
- 40年間の歩みから学ぶ持続可能な雇用環境の整備方法
- 知的・身体・精神障害の特性に応じた3種類の働き方支援
- 業務内製化が生む雇用創出と生産性向上の好循環メカニズム
- 専門設備が不要なクリーニング業界の雇用拡大ポテンシャル
背景と事例の概要
「社会が変わる時、企業はどう対応すべきか?」この問いが業界の変化を加速させました。衣料品管理の現場で今、再利用文化が根付く中、新しい働き方が生まれています。
業界構造の変化と雇用創出
2000年代以降、環境意識の高まりが業界地図を塗り替えました。使い捨てからリユースへ転換する動きが、専門サービス需要を2.3倍に拡大させています。この流れを受けて、多くの企業が外部委託から自社業務への切り替えを進めました。
| 時期 | 内製化率 | 雇用増加率 |
| 2000年 | 32% | +8% |
| 2010年 | 57% | +19% |
| 2020年 | 74% | +31% |
支援の始まりと成長
ある企業の転機は20年前に訪れました。当時の社長が友人から「働ける場所を作れないか」と相談されたことがきっかけです。人材不足解消と社会貢献を両立させるため、障害のある方々の採用を決断しました。
最初は戸惑いもありました。スタッフの8割が初めて接する状況でしたが、試行錯誤を重ねるうちに独自の指導法を確立。現在では、特性に応じた3つの支援体制が機能しています。
この取り組みが示すのは、企業成長と多様性尊重が両立可能だということです。次の章では、具体的な成功事例を掘り下げていきます。
障がい者雇用 クリーニング 内製化 の取り組み事例
職場の定着率が平均3年と言われる現在、ある企業では40年間同じ現場で働き続ける方がいます。この数字が示すのは、単なる雇用ではなく持続可能なキャリア形成の実現です。

某クリーニング企業の取り組みと実績
全従業員28名が正社員として活躍しています。勤続10年以上のベテランが半数を超え、中には創業時から働く方もいます。「それぞれのペースで成長できる環境」が、長く働き続ける秘訣です。
給与体系にも特徴があります。6ヶ月ごとの昇給制度を導入し、平均工賃は45,737円に達しています。これは地域の平均を15%上回る水準で、働く意欲を支える重要な要素となっています。
いろどり事業所と他事例との比較
時給1100円からスタートする昇給システムは、目標達成の喜びを感じながら働ける仕組みです。一般企業との大きな違いは、業務内容の柔軟な調整にあります。
就労継続支援事業所では個別の能力に応じた作業を設定可能。対して一般企業では生産性向上が求められますが、双方の良い点を組み合わせたハイブリッド型が注目されています。
ある従業員はこう語ります。「ここでは自分の特性が強みになる」。多様性を活かす職場づくりが、企業と従業員双方に良い循環を生んでいるのです。
設備面と作業方法の工夫

最新技術と現場知恵の融合が、働きやすい環境を作り出しています。ある工場では、複雑な工程を直感的な操作に変えることで、誰もが能力を発揮できる仕組みを実現しました。
自動プログラムと数量管理システム
ICチップを活用した管理システムが業務を変革しています。病院のユニフォームに埋め込んだチップを読み取ることで、数量確認が瞬時に完了。従来30分かかっていた作業が、たった3秒で正確に処理できるようになりました。
| 項目 | 従来方法 | 新システム |
| 数量確認時間 | 30分 | 3秒 |
| 誤差発生率 | 2.1% | 0.03% |
| 必要な作業人数 | 3名 | 1名 |
洗剤投入から仕上げまでの改善策
洗濯機の自動プログラムが作業負担を軽減。洗剤の計量から投入までを完全自動化し、ボタン1つで全工程が完了します。ある従業員は「間違いが心配だった計量作業から解放された」と語ります。
シーツ管理では両端を挟むだけで機械が自動処理。ビデオメジャーが0.1mm単位で品質をチェックし、人間の目では見落としがちな微細な損傷も検知します。
誰でも使える操作インターフェース
コントロールパネルには色分けとピクトグラムを採用。操作手順を視覚的に理解できる設計で、初めての方でも迷わず作業できます。ある管理者は「マニュアルがなくても直感的に使えるのが最大の強み」と評価しています。
重量チェック機能付きの乾燥機では、規定範囲外の製品を自動的に選別。この仕組みにより、工程間の連携ミスが75%減少しました。
社内支援体制と生活支援の実践事例

職場と生活の両面を支える仕組みが、働く意欲を持続させる秘訣です。ある工場では、作業指導と日常生活支援が連動した独自のシステムを構築しています。
指導員配置と社内コミュニケーションの強化
各現場に配置された専門指導員が、個別の特性に合わせた作業指導を行っています。1人の指導員が最大3名を担当し、週に1度の進捗確認ミーティングを実施。ある従業員は「分からない時すぐ相談できる安心感がある」と語ります。
季節ごとの交流行事がチームワークを育んでいます。夏の海水浴旅行ではスタッフ全員が参加し、クリスマス会では役職関係なく笑顔が溢れます。「仕事以外の場で仲良くなるから、普段の連携がスムーズになる」と管理者は実感しています。
生活面のサポート体制と寮・グループホーム連携
地域福祉団体と連携した居住支援が特徴的です。2つのグループホームでは、食事管理から金銭管理までを専門スタッフがサポート。児童養護施設出身者への生活指導も行っています。
障がい者スポーツ活動を通じた健康管理が成果を上げています。過去には卓球選手が世界大会で入賞し、バスケットボールチームが全国大会出場を果たしました。あるアスリート社員は「練習と仕事の両立が自信につながった」と話します。
保護者の高齢化に対応した新たな居住施設も整備中です。職場と自宅を往復するだけでなく、地域社会とのつながりを大切にした支援体制が評価されています。
経営合理化と生産性向上への効果
多様な人材が主役となる職場が、企業の競争力を高める新たなモデルを生み出しています。あるリネン管理企業では、働き方の改革が生産性40%向上と人件費15%削減を同時に実現しました。
業務プロセスの見直しと効率化の効果
22年間同じ現場で働くAさんの事例が示すのは、継続的なスキル蓄積の威力です。顧客情報の記憶力と正確な作業手順が、新人スタッフ3人分の業務量を1人で処理可能にしています。
工程の細分化と自動化が相乗効果を発揮。洗濯物の仕分け時間が従来の1/5に短縮され、機械操作の誤作動も98%減少しました。これにより、少人数チームでの高品質生産が定着しています。
多様性が生む経営的メリット
従業員の定着率向上が最も顕著な効果です。離職率が業界平均の1/4に抑えられ、採用コストの削減に直結。安定した人材基盤が、受注変動への柔軟対応を可能にしています。
ある管理者は「想定外の能力が新たな価値を生む」と指摘します。記憶力に優れたスタッフが在庫管理を革新し、視覚特性を活かした検品体制が不良品率を0.1%以下に抑えています。
FAQ
業務効率化と多様性配慮を両立するポイントは?
自動化システムの導入と従業員の特性に合わせた作業設計が重要です。新陽ランドリーでは洗剤計量機の色分け表示や工程チェックシートを活用し、誰でも正確に作業できる環境を整えています。
生活面での支援体制はどうなっていますか?
寮と連携した24時間サポート体制を構築。いろどり事業所では指導員が通勤同行や健康管理を実施し、グループホームと連携して安定した生活基盤を提供しています。
生産性向上に効果的な取り組みは?
洗濯物の重量管理システムと工程見える化が効果的です。数量を数値化して進捗を可視化することで、スタッフの意欲向上と業務改善の両方を実現しています。
業務改善で特に評価された事例は?
シーツ専用仕上げたたみ機の開発が注目されました。複雑な工程を単純化し、品質基準を維持しながら作業負荷を30%削減することに成功しています。
コミュニケーション強化の具体策は?
毎朝のミーティングと図解マニュアルを併用。視覚的な情報伝達と対話を組み合わせることで、情報の共有精度が向上したとの報告があります。
経営面でのメリットはどのようなものですか?
人件費の最適化と離職率低下が顕著です。ある企業では3年間で生産性15%向上と人材定着率90%超えを達成し、持続可能な運営モデルを構築しています。